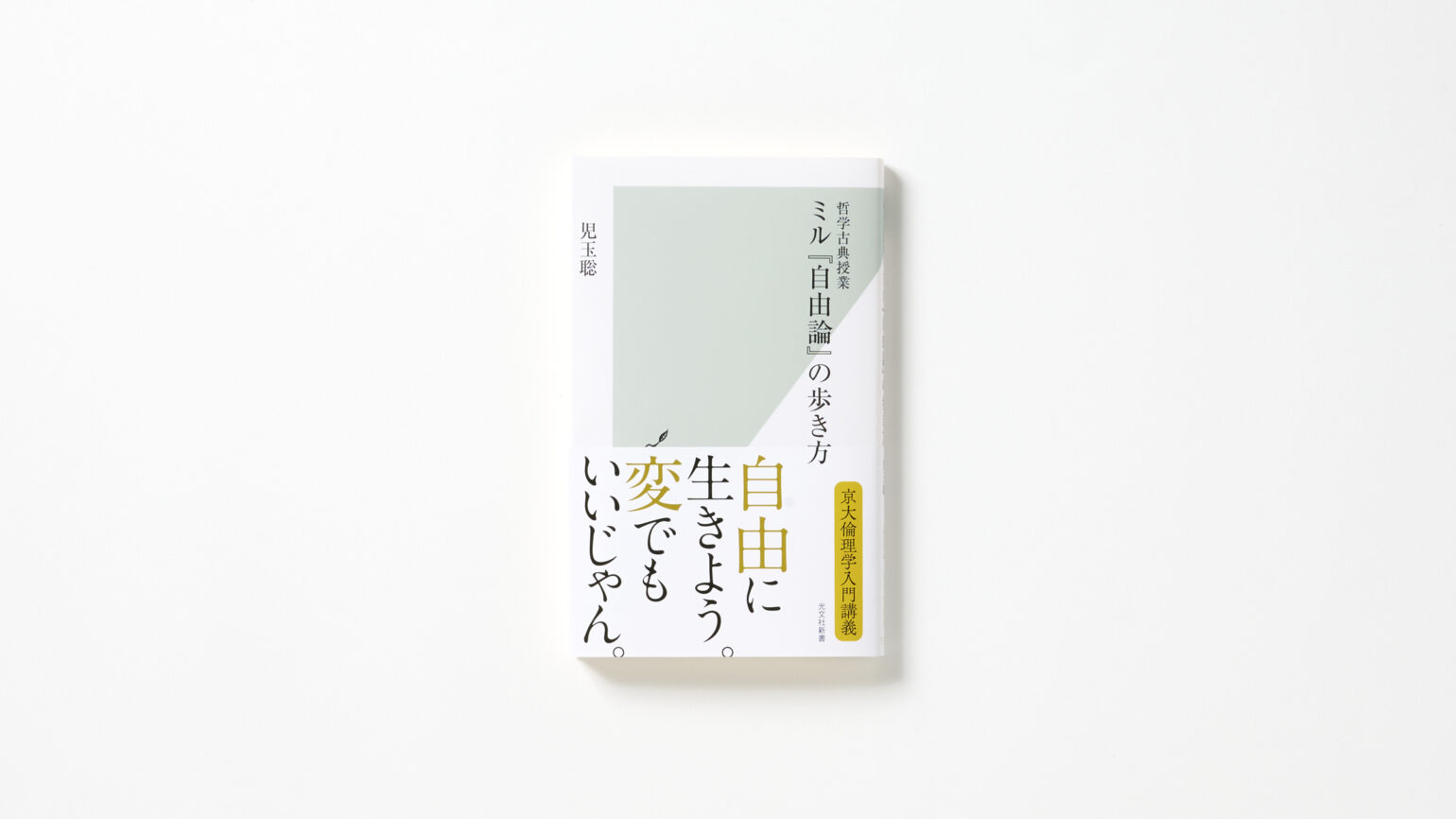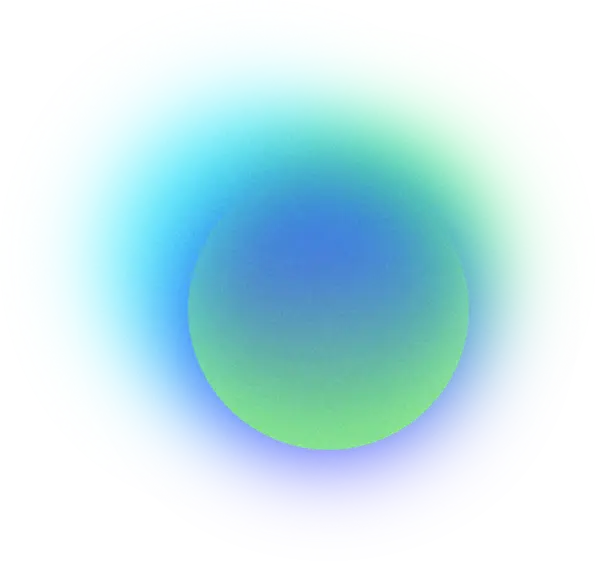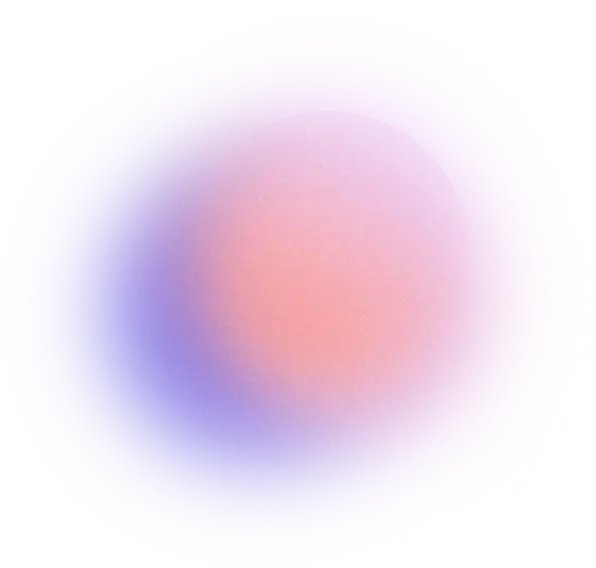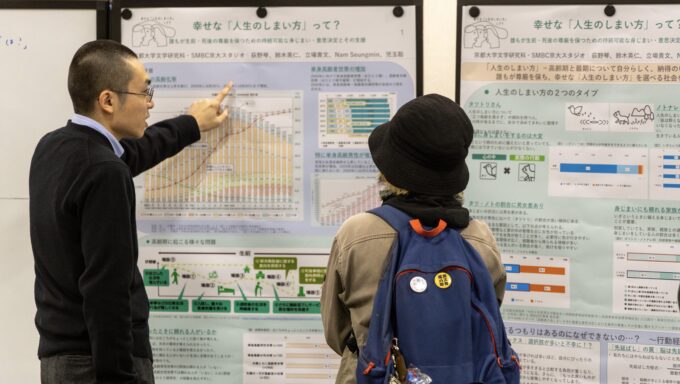児玉先生にはじめて執筆依頼をしたのは、2020年、新型コロナウイルス最盛期の夏でした。
その少し前まで、わたしは長らく週刊誌の編集をしていました。十数年間にわたってほとんど毎週休むことなく、芸能人の取材やら掃除のティップスやら全国のかわいい猫ニュースやらウーパールーパーの唐揚げの作りかたやら、「今この時」のみにフォーカスした企画を立て続ける生活をしていたおかげで(?)、このうえなく世俗的な脳になっていました。
アカデミアの知識がまったくない状態で新書編集部に異動して、本になる企画を探し回る日々の中で出会ったのが、京都大学のオンライン講座『立ち止まって、考える』です。「こんなにおもしろくて役に立つ授業が、家でいつでも(しかもタダで)見られるなんて!」と感動して毎日のように視聴し、児玉先生の講義「パンデミックの倫理学」を拝見したのが、本書の企画が始まった最初の瞬間です。
新書の著者はその大半が研究者の方々ですので、編集者はいい書き手を探して、しょっちゅう大学界隈に出没しています。といっても、リアルに学校を歩き回っているのは打合せやフォーラムのときくらいで、ほとんどはネットの研究者紹介ページをうろうろして、そこから論文やオンライン講義に飛んだり、興味を惹かれた方の著書を読んだりして、アプローチする著者を探します。企画立案の仕方は大きく二通りで、まずは自分の興味から企画を立て、書いてくれそうな著者を探す企画ありきパターンと、「この人に書いてほしい!」という魅力的な著者ありきで企画を考えるパターンがあります。
以下はあくまで弊社の場合ということになりますが、光文社新書は一般の読者を意識したレーベルですので、論文や教科書の文章を読むだけでは著者との相性を測りきれない部分があります。よって、大学の教員紹介ページや研究者紹介プラットフォームなどに一般向けの文章や動画が載っていると、企画の具体化に役立ちます。若い方は研究者紹介プラットフォームに研究者としての矜持やアウトリーチへの意思、インタビューリンクなどを載せている場合も多く、論文以外の情報として大変参考になります。
児玉先生にオファーしたときは、オンライン講義をそのまま新書化する真面目企画と、哲学者を人物像から一般読者に紹介するちょっと軽い企画と、両方をもってご相談しました。当時、児玉先生が明石書店のウェブサイトに連載(のちに書籍化)されていた『オックスフォード哲学者奇行』の文章が、すごく軽やかで良かったからです。
その後もウイルスがまた蔓延したり先生がご多忙を極めておられたりで、ようやく先生にお会いできたのは2023年の10月でした。どの企画で進めるかからご相談していた際に、先生が大学で担当されている哲学古典を教える授業のお話をしてくださいました。
哲学の古典というのは、誰もがその重要性を認めているにもかかわらず、現代社会を生きる多くの一般人は、手に取りません。いかにも難しそうで、時間がかかりそうで、マルチタスクの生活の中でわざわざその高い認知的負荷をとろうとは思わないからです。それでいて、読んでいないことに対するちょっとした後ろめたさを感じている人も多いのです(わたしとか)。
そして、先生が授業で取り上げられていたミル『自由論』は、世俗にまみれた現代人(わたしとか)にこそ必読の書であると感じました。「自由」ついてはSNSやテレビなどで毎日のように議論されていますが、そもそも「自由とは何か」の定義をせずにやり合っているので、不毛です。今から160年以上も前に「個人の自由の限界はどこにあるか」「なぜ個人の自由が重要なのか」ということを徹底的に考え抜いた本が『自由論』であるというお話を伺い、自由についての不毛な議論が蔓延る現代にこそ本書のガイドブックを出す意義があるだろう、ということでテーマが決まりました。
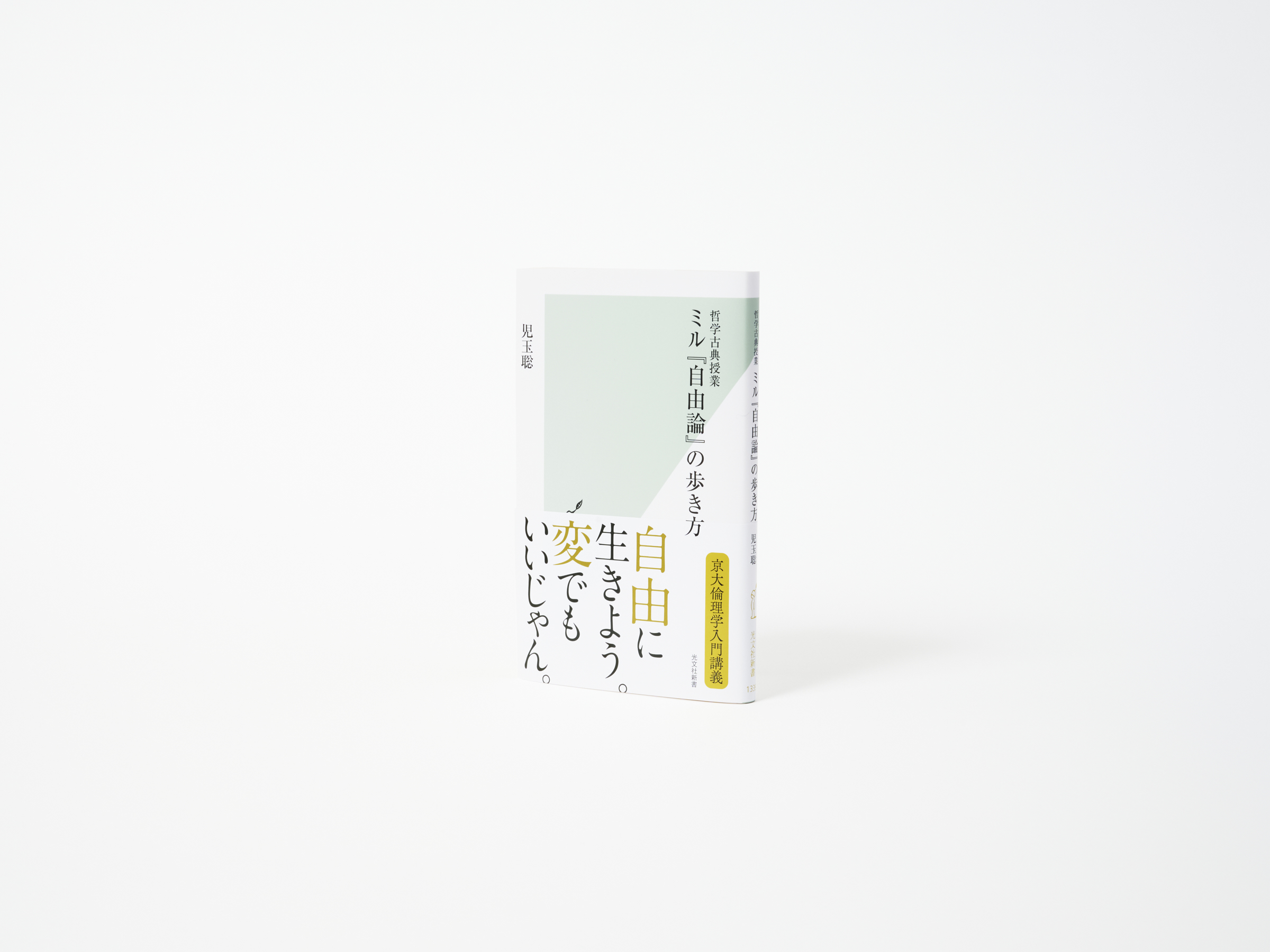
とはいえ、光文社新書は一般向けの本です。世俗にまみれた一般人(わたしとか)が「おもしろい」と感じるものでなければ、多くの人に手にとっていただくことはできません。その意味でもこの企画がいいと思ったのは、ミルの「ヤバい人」エピソードがおもしろかったからです。
ミルは小学校すら行かず、哲学者である父親によってかなり特殊な英才教育を受けている(3歳からギリシア語を習い、7歳からプラトンを勉強)ので、友達に会う習慣も、芸術にふれる機会もなく育っています。そんなミルが「女性についてはほとんど赤ん坊にひとしい」状態で恋をしたのが、ハリエット・テイラーです。当時、ハリエットはすでに結婚していたので、その後20年ほどの長きにわたって、ミルと彼女はいわゆる「不倫」をしています。
ハリエットの夫の死後にようやく結婚できた二人が、共同執筆ともいえる形で書いたのが『自由論』です。しかし、ハリエットは旅先のホテルで体調を崩して亡くなってしまいます。結婚生活はわずか7年半。悲嘆にくれたミルは、ハリエットの墓が見える場所に家を買い、ハリエットと最期の時を過ごしたアヴィニョンのホテルの家具を買い取って、ハリエットの娘に世話をしてもらいながら、そこで晩年を過ごすのです。
見方によってはロマンチックですが、相当に極端な人です。❝プラトニック不倫20年❞というのもすごいし、ホテルの家具を買い取って自分の家で使っちゃう、というのもすごいです。尋常ならざるグリットです。
極端だからこそ、興味もわきます。書いた本より先に、書いた人自身のおもしろさや人間臭さに興味を惹かれることも、古典を読む動機の一つになるかと思います。そのため、本書の推敲の際には「ミルの人となりが書かれてない! 知られざるエピソードとか、探せばもっとあるでしょ!」と(いう趣旨のことを丁寧体で)お願いし、つねに締め切りに追われる児玉先生をさらに追い詰めた日もありました。
こんな風にして『哲学古典授業 ミル『自由論』の歩き方』は誕生したのです。
文=永林あや子